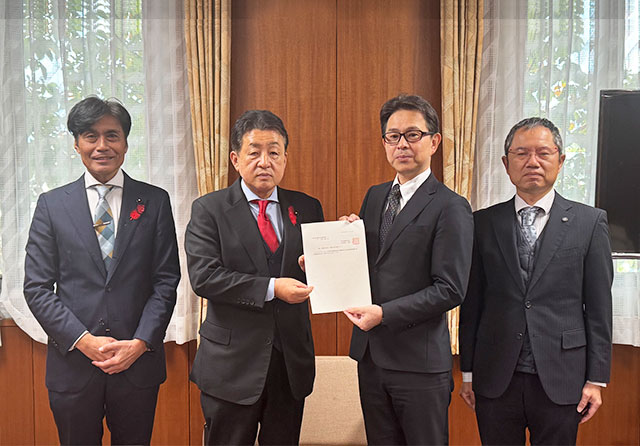県政ニュース93号2025年春を発行いたしました。
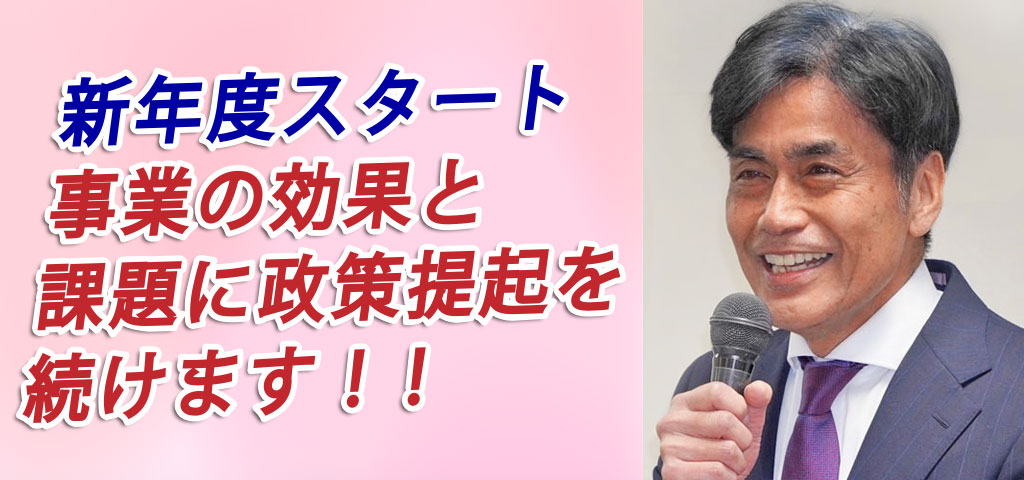 春暖の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
春暖の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、木村県知事就任後初の一般会計当初予算案を審議する2月定例県議会は、3月19日に閉会しました。
2月定例県議会で可決した新年度当初予算は8448億円で、当初予算には木村知事の「くまもと新時代共創基本方針」で目指す「こどもまんなか熊本」の実現をはじめとする取組みに関する事業予算が計上されています。取組の目標は「県民みんなが安心して笑顔になり、持続的で活力ある熊本の未来を共に創る」として、重要なキーワードとして、「世界に広がる」「人を育てる」「共に創る」が掲げてあります。
その主な取組の基本的方向性①の「こどもたちが笑顔で育つ熊本」に向けては、オンライン教育支援センターの設置、県営住宅における子育て世帯向けの改善、こども食堂や地域の学習教室などのこどもの居場所づくりに要する経費、産後ケア事業などに40億円。基本的方向性②の「世界に開かれた活力あふれる熊本」には、熊本多文化共生支援事業、半導体サプライチェーン参入促進支援事業、食のみやこ熊本県の創造に向けた取組、農業の担い手確保・育成、運動公園駐車場の整備などに94億円。基本的方向性③の「いつまでも続く豊かな熊本」には、地下水の監視体制の強化やP F O SやP F O Aなど有機フッ素化合物のモニタリング調査や分析等の経費、地方公共交通バスの維持・確保などに14億円。基本的方向性の④の「県民の命、健康、安全・安心を守る」には、救急安心センター(#7119)の運営、電話で「お金詐欺」等被害防止対策の推進などの経費で171億円などとなっています。
私たち立憲民主連合は、当初予算には川辺川ダム本体着工に向けた国直轄事業の県負担が含まれていたので、私から「住民団体が求める共同検証もしないまま事業を強行しているので認められない」と討論をした上で反対しました。
また議員提出議案で自民党・参政党が提出した「旧姓の通称使用の法制度の創設を求める意見書」に対して、夫婦別姓を望む人の声を断ち切る内容であるため西県議が反対の意見を述べた上で反対しました。
その他、議員提案の「熊本県いぐさ・畳の振興に関する条例」については全会一致で可決しました。
私が所属する高速交通ネットワーク整備推進特別委員会では、空港アクセス鉄道について、これまで令和6年度内に事業費やB/C(費用対効果)、ルート案を示すとされていましたが、J R豊肥本線沿線への企業や人口の張りつきや物価高騰などの状況を鑑みて9月議会で示すと公表時期を延期しました。私からは豊肥本線沿線に企業が張りついたとしても大津駅から空港までの乗客数は大きく変わらないのではないか、ルート案については地下水などの環境への影響に対する懸念があるので早く示して議論をすべきと強く求めました。
経済環境常任委員会では、NTT桜町ビル解体工事に伴い敷地内にある熊本県物産館については、解体工事が開始されて安全上の問題もあるので早期に移転等の方針を決めて対応すべき、令和9年度事業開始を目指して半導体企業向けの水確保のため菊池の竜門ダムから新たな工業用水道整備(150億円)の採算の見通しについて、これまで県の工業用水事業は需要があると見込んで整備して赤字になっている。企業は地下水を使えば無料ですが、今回整備される工業用水を金を出して使用するのか疑問なので半導体企業に対して使用を強く求めるべき、などの意見を提起しました。
その他、主な特徴点は以下のとおり
○渋滞対策
・熊本都市圏北東部エリアをターゲットに30箇所の交差点改良を3年以内、80箇所を10年以内に実施する。
・1万人のオフピーク通勤を1年以内に実施。公共交通利用を10年以内に2倍にする
・都市圏3連絡道路の具体化に向けてルート案を本年中に示す。
・JR豊肥本線の乗車率は、R4は135%、R5は125%。複線化の協議を加速化する
○令和6年度の企業誘致は、立地協定件数は44件でそのうち半導体関連企業は14件。
○本県における訪日外国人延べ宿泊者数は、令和6年は約144万人と過去最高 など
○熊本県菊陽町の周辺では2024年12月末までに、239ヘクタールの農地が工場用地などに転用。10市町村で貸借可能な2100筆の農地情報を県のデータベースに登録し、これを基にマッチングなどで56ヘクタールの代替農地を確保。今後さらにまとまった農地を確保するため、林地の農地化も検討する。
以上の新年度の事業推進にあたりその効果と課題に対して、県民目線で必要な政策提起を行なっていきますので、引き続きご意見をお聞かせください。